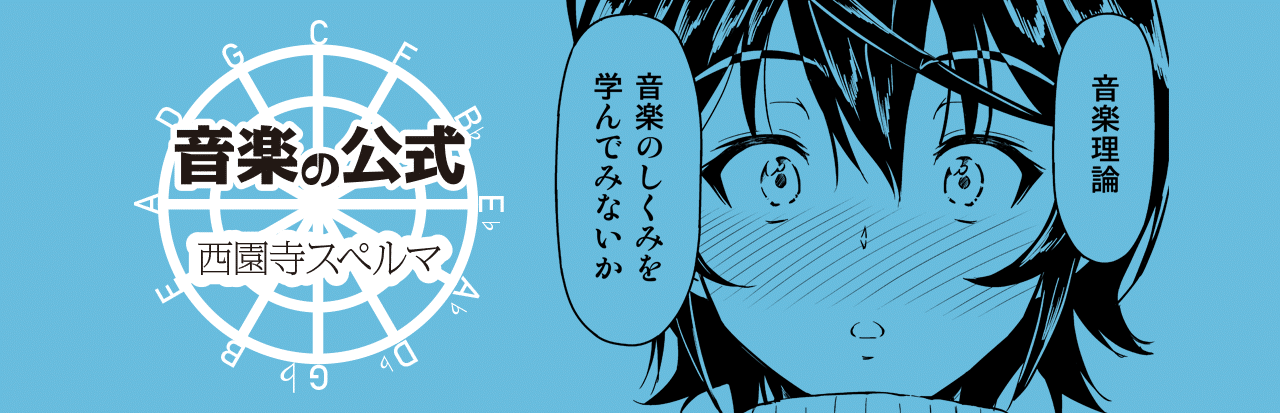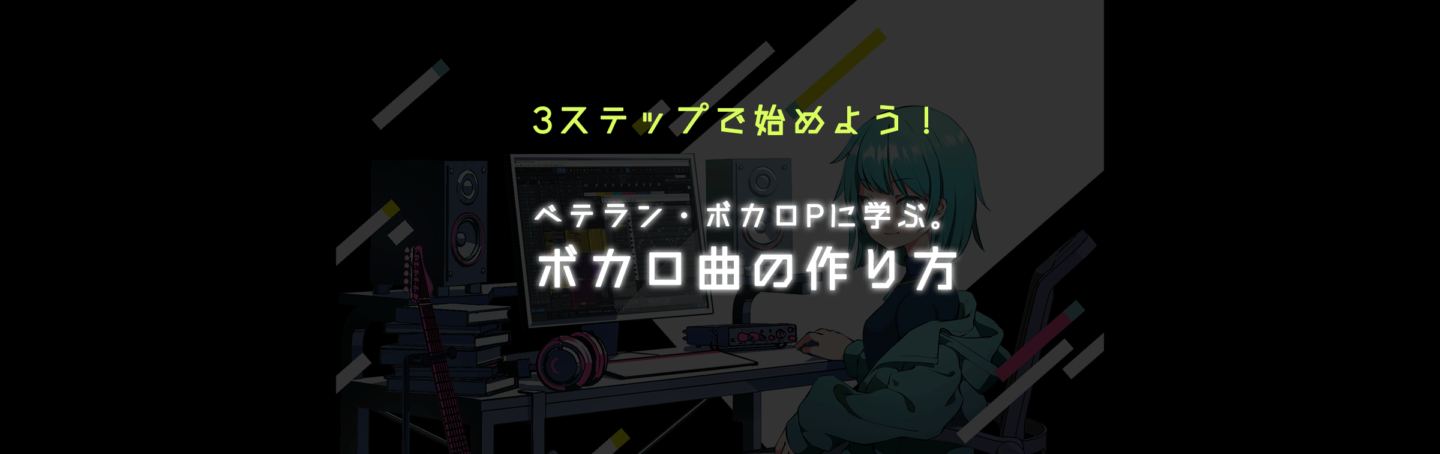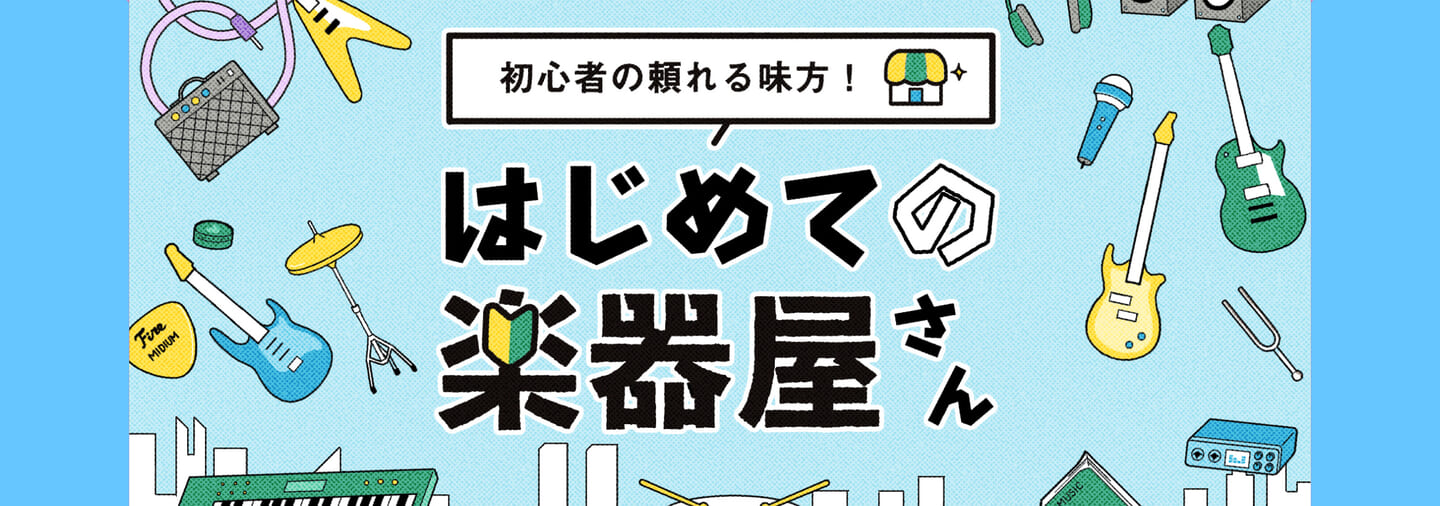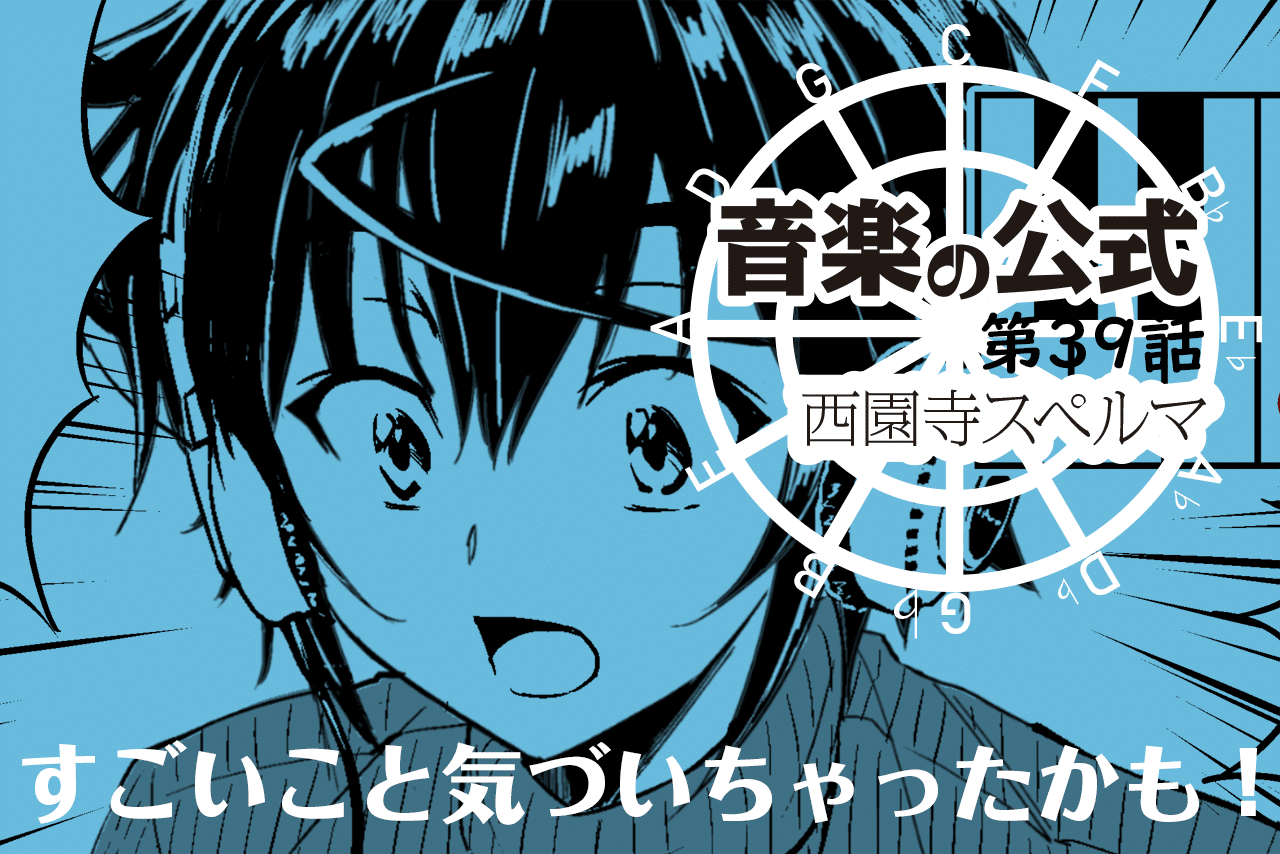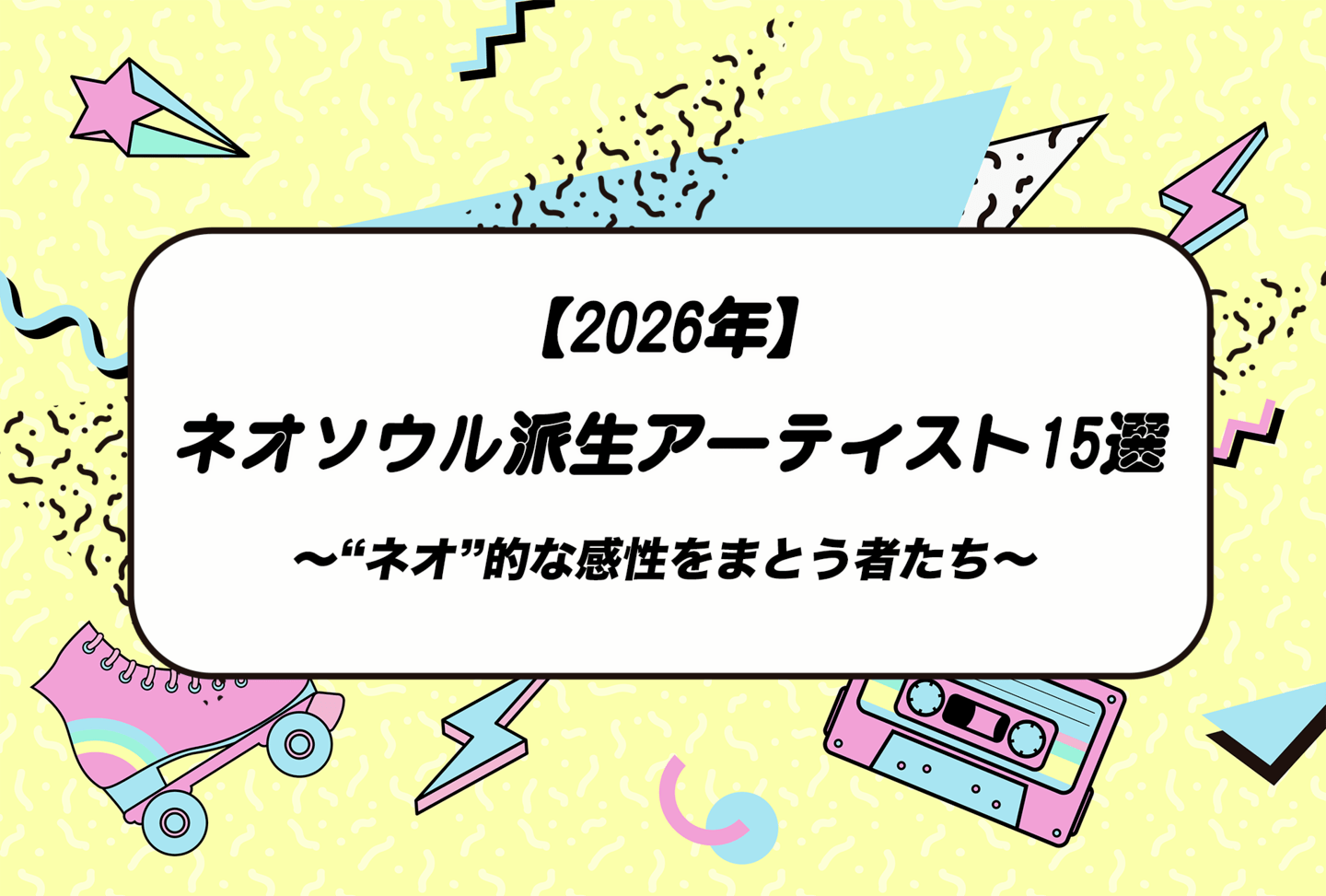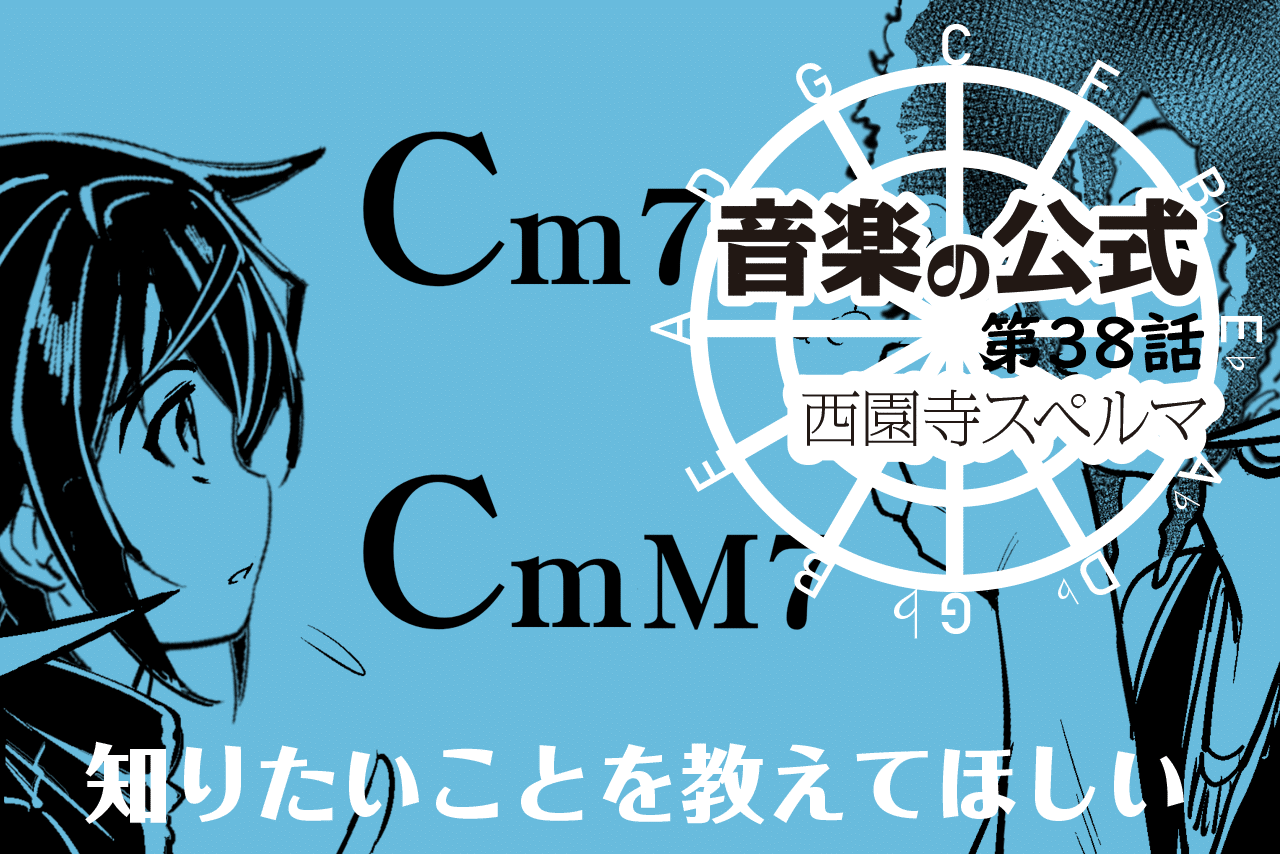文:ぱりぱりさらうどん
編集:濱田侑佳(plug+編集部)
画像:文章内にURLを記載
目次
はじめに

さて今回も前回と同様、“ボーカロイドを使って音楽を制作することがどれだけ幅広い可能性に満ちているか”について実際のボカロ曲を例に挙げながら考えていきたいと思っています。その中でも今回は特に初音ミクに焦点を絞って、初音ミクのキャラクター性についても考察していこうと思います。
初音ミクのキャラクター性について考えるにあたって、紹介したい楽曲があります。
それは、ボカロPのピノキオピーさんが2023年に公開した「匿名M」です。この楽曲はライターのARuFaさんが匿名M(初音ミク)にインタビューをする形式で曲が進行します。楽曲の中で匿名M(初音ミク)は、独自の人格を持つ存在として描かれつつも、<人間のふりしてる、ただの音楽ソフトです。>、<まあ全部、言わされてるんですけど。>といった言葉によって、その人格があくまで演出に過ぎないことが、メタ的に示されています。自己を“音楽ソフト”とアイデンティファイする行為自体もまた人間が勝手にしたことなのです。
この楽曲でも分かるように、初音ミクには明確なキャラクター設定がありません。楽曲ごとに異なる初音ミクが存在し、各々の初音ミクは自ら意志を持って言葉を発することはなく、人間によって与えられた言葉を発声します。この、誰がこの言葉を発しているのかが不明瞭な点において、ボーカロイドを使って楽曲制作をすることは、匿名性の強い表現方法であると言えると思います。
名前を与えられ、キャラクター性を与えられながらも、決して固定された存在にはならない不思議な存在、初音ミク。だからこそ私たちは、初音ミクにあらゆるものを託すことができるのです。「匿名M」曰く、<命の無い私に、あなたはどんなイメージを着せる?>。
私はこの“特定できない初音ミク”という概念が大好きです。本稿では初音ミクのキャラクター性が“特定できない”という前提を踏まえたうえで、4作品ほど紹介しながら、実際に楽曲の中で初音ミクがそれぞれどのように機能しているのかを考察していきます。
また、今回も前回と同様、具体的に作品のレビューをしていきますが、“作者はこう考えて作ったに違いない!”と主張することはないのでよろしくお願いします。作品やクリエイター、リスナーの数だけ、無数に初音ミクは存在すると私は思っています。だからこそ、あなたの思う初音ミク像を、これから私が言うものに“特定しないでね。”。
八王子P 「気まぐれメルシィ feat. 初音ミク」
プレイヤーとしての初音ミク
めちゃくちゃかわいい曲ですよね。PVも最高。“もっとアタシのことを見てほしい”という乙女心を、初音ミクが歌って踊って表現しています。この曲で私たちは、八王子Pさんが初音ミクを “振り回されっぱなしの女の子”と表現していることを理解しながらも、私たちはこれをリアリティのある話としては受け止めていません。なぜなら初音ミクは人間ではなく音楽ソフトであり、物語的な背景設定もないからです。
だからと言って、振り回されっぱなしの女の子として描かれる初音ミクに、“演じているだけ”や“偽りだ”などと考える人は少ないと思います。構造として近いのは、アイドル。例えば、アイドルが恋愛ソングを歌って踊るとき、私たちは恋愛ソングの主格がその曲の作り手(作詞家や作曲家など)だとは思いません。私たちは恋愛ソングの主格を表現者であるアイドル自身に求めながらも、その恋愛自体がフィクションであることを知っています。
ボーカロイドとアイドルとで明確に違うのは、やはりボーカロイドは人格を持たない存在であるということ。アイドルはあくまで一人の人間であり、個人としての人格や経験を持ちながら、楽曲の世界観を表現するのに対し、ボーカロイドは音楽ソフトであり、楽曲ごとに異なるキャラ設定やストーリーを与えられるものの、それ自体には人格や主体性がありません。主体性があると、良くも悪くも作品の解釈に影響を与えます。例えば、アイドルが恋愛ソングを歌う場合、リスナーは無意識のうちに“この曲を歌うアイドルは実際のところ、この歌詞をどう思っているんだろう?”などといった疑問を持ってしまうことがあると思います。人格を持つ存在であるアイドルが歌う行為そのものが、ノイズになり得るのです。※1
人間は主体性を持っているからこそ、アイドルが与えられた曲を歌わされているという主体性が曖昧になりかねない構造に対して、人によっては忌避感を覚えることがあると思います。対して初音ミクの場合、歌わされる存在であることが当たり前過ぎて、私たちは逆説的にその構造を意識しません。初音ミクはこの楽曲で振り回されっぱなしの女の子として振る舞うことに対して何の抵抗も示さないし、そこに演技という概念すら介在しない。だから初音ミクは、振り回されっぱなしの女の子として振る舞うプレイヤーとして機能する上で、限りなくノイズが少ない存在なのです。
※1 本稿における“歌わされている”という表現は、アイドルが自分の意思に反して楽曲を歌わされているという意味ではなく、楽曲の制作プロセスにおいて、作詞/作曲/プロデュースといった複数を担当する他者の要素が演奏に関与していることを指しています。しかし、これはアイドルの表現活動の主体性を否定するものではありません。むしろアイドルは自分自身の表現力を活かし、パフォーマンスによって楽曲に命を吹き込む存在であり、人間が持つ主体性の豊かさを示す存在でもあることは理解の上で言及しています。
ピノキオピー「シックシックシック feat. 初音ミク」
普遍的存在としての初音ミク
この曲では、病気というテーマを通じて、正常と異常の境界が曖昧であることが描かれます。人間の感情や行動が医学的な病名と結びつけられ、恋をすること、感動すること、夢を見ることすら病気として分類されてしまう。私はこれを、個々の生きづらさが“異常”としてラベリングされ、時に病理化されてしまうことへの風刺的な表現であると思っています。実際に歴史を振り返ると、LGBTQ+ の人々が精神疾患として診断されていた時代があったり、左利きの人が矯正されていたことがあったり……と、マイノリティであることが病気とみなされてきた事柄が多く存在します。よって私は「シックシックシック」の中で繰り返される<シック>という言葉は、病気というよりも、“社会が決めた異常者”を象徴していると考察しています。
では、もし異常とされるものが、人間の本質的な感情や行動であるならば、私たちの正常とは、一体何を指すのでしょうか。その問いをメイン・ボーカルとして歌うのは、人間ではありません。初音ミクです。
初音ミクには生まれや育ちも、個人的な経験や価値観もありません。もしこの曲をメイン・ボーカルで歌っているのが人間であった場合、リスナーは無意識のうちに“この人自身、どのようなマイノリティ性を抱えているのか?”という考えから、この楽曲の異常性を個人の物語として受け取りやすくなります。しかし初音ミクの場合、そこに個人的な背景は一切介入しません。初音ミクは、すべての人間の代弁者になれるが、特定の誰かにはならない。この初音ミクの特定性のなさが、この楽曲のメッセージが“特定の個人の苦悩”ではなく、“すべての人間が抱える普遍的な異常”として響く理由なのだと思います。
ここで着目したいのが、楽曲中で作者であるピノキオピーさんの歌声が、ボーカロイドである初音ミクの歌声と部分的にハモるという点です。ハモっているという点で、この楽曲においてピノキオピーさんの歌声は初音ミクと対等なものではなく、あくまで補佐的な役割として寄り添うように配置されていると仮定すると、初音ミクの声がすべての人間が抱える普遍的な異常、ピノキオピーさんの声が個人的な苦悩や異常の表現として機能していると考えたとき、このハモリは個人的な異常を普遍的な異常の中へと埋め込む行為と考えられます。個人の異常が個別のものとして分離されるのではなく、普遍的な異常の中へと包み込まれることで、異常の境界が曖昧になり、異常は特定の誰かのものではなく、全員のものとして扱われるようになる。そして異常という概念そのものが“誰のものでもないもの”として浮かび上がってきます。
さらに、この曲の最後に繰り返される<もう みんな病気だよ>というフレーズ。一般的に異常とは、普通があるからこそ成り立つ概念です。しかし、もし異常がすべての人間に共通するものであるならば、それはもはや異常と呼ぶことはできないのではないでしょうか。みんなが異常であるなら、それはただの人間の本質なのではないでしょうか。
2番サビ前までは、ボーカロイドと人間の声が重なることで、異常の普遍性と個別性を同時に表現する仕組みになっていました。しかし2番のサビ後には<こんにちは 元気ですか>から始まる一節で、唯一ピノキオピーさんの声だけになる瞬間があります。この部分で、個人的な異常は普遍的な異常から一瞬だけ分離され、単独で浮かび上がります。私はこの変化には、ピノキオピーさんがリスナーへ直接語り掛けるという、メタ的な呼び掛けとしての意味があるのではないかと考えました。それは楽曲の中の語りではなく、楽曲そのものに対する語りとして。異常を抱えるクリエイターから、異常を抱えるリスナーへの問い掛けとして。
呆「あふれそうだよ/ feat.初音ミク」
他者としての初音ミク
シンプルなバンド・サウンドの中に、穏やかでありながら深く引き込まれるようなロックの響きがある楽曲。MVの概要欄には、“初音ミクとバンドをやりたい。”と一言記されています。私はこの言葉には、ミクを自由に操るものとして扱うのではなく、作者自身とともに音楽を奏でる仲間として受け入れたいという願いが込められているのではないかと思いました。以下でそう考えた理由を述べていきます。
MVイラストを観てみましょう。ギターを弾きながら歌うミクは、決して私たちと目を合わせることがなく、ただただマイクの向こう側を見つめているようです。一般的に多くのボカロ曲のMVでは、ミクの視線をリスナーに向けることで、ミクが私たちに向かって歌っているように感じさせる演出がされています。しかしこのMVのミクはこちらを見ず、ただ歌い、演奏し、そこに居る。このカメラ・アングルはまるで、ミクのバンド・メンバーの視点を映し出しているかのようでもある。このことから私は、楽曲制作者はこの映像で、ミクをプロデュースする視点ではなく、一緒に演奏するバンド・メンバーとして捉えていることを表現しているのではないかと考えました。
当然ですが、初音ミクはボーカロイドであり、人間ではありません。同じ言語を話していても、その意味を理解しているわけではありませんし、ミクの声に感情を感じたとしても、ミク自身は何も思っていません。それでも、私たちは初音ミクの歌に共鳴し、そこに意味を見出してしまう。
ともに音楽を奏でることができても、決して理解し尽くすことのできない、他者としての存在。初音ミクは、私たちの隣に居るが、決して振り向かない。
yanagamiyuki「サイバーかわいくないガール / 初音ミク」
代弁者としての初音ミク
この楽曲では初音ミクの一人称が、“私”と“おれたち”の間で揺れ動きます。<私サイバーかわいくないわ>とミクが歌うと、あたかもミク自身の言葉のように聴こえますが、<サイバーかわいくねーおれたち>となると、語り手はミク個人ではなく、おれ“たち”という集団へと変化するように思います。私はこの“おれたち”とは、楽曲制作者である yanagamiyukiさんをはじめとする、楽曲に共鳴するすべての人々を指しているのではないかとも考えています。つまり初音ミクは、“私”として語りながらも、実際には“おれたち”の思いを背負う、代弁者としても機能しているのです。
この楽曲の歌詞の一節に、<初音ミクひとりとシェアして 倍使用している心臓を>という言葉があります。ここで言う<心臓>を感情や生の証として捉えると、私たちは自分の言葉では伝えきれない思いを、初音ミクという存在に託し、ミクと心臓をシェアすることで、表現の手段を得ていると考えられる。これは歌わされるという行為を超え、感情を伝えるためのつなぎ役としても初音ミクが存在しているということだと思います。
ここで、この曲のMVに引用されている、ピーテル・ブリューゲルの絵画作品『死の勝利』について考えてみましょう。この16世紀の絵画には、骸骨の兵士たちが人間を無差別に襲い、死が世界を支配する様子が描かれています。
『死の勝利』のテーマは、死の絶対性、人間の無力さです。しかし今日のデジタル時代において、死は必ずしも、終わり、消滅ではなくなりました。インターネットに残されたデータは、個人が死んだ後も消えることなく、時には拡散され続けます。初音ミクは、こういった“死ねない世界”の象徴です。初音ミクはボーカロイドであり、肉体的な死を持ちません。ミクの声はデータとして保存され、未来へと残り続け、誰かが歌わせる限り永遠に“私”として語ることができる。しかしそれは本当に、生きていると言えるのでしょうか。
「サイバーかわいくないガール」には、<誤解はもう誤解のまま>という歌詞があります。私はここでは作者の、“自分が伝えたかったことが伝わらないまま消えてしまうこと”への恐れが表現されているのではないかと思いました。SNSでは誰もが発信できる一方で、言葉が誤解され、真意が届かないまま広まってしまい、一度拡散された言葉は制御できず、正しく伝わらないまま未来永劫残ってしまうことも多い。こういった不安を死ねない初音ミクが代弁することで、ミクは“死の外側にいる存在”として立ち現れるのです。
ミクは“私”として語りますが、その言葉は私たち人間の、“おれたち”のものです。ミクは死の恐怖を歌いますが、それは私たちの恐怖です。そして、ミク自身は死なない存在でありながら、生きているとも言えません。その曖昧な立ち位置こそが、デジタル社会における、終わらない存在としての象徴なのではないでしょうか。
初音ミクはこの曲で、人間の声を代弁し、終わらない存在としての問いを投げかけます。
最後に
“初音ミクとは誰なのか”。こうした問いは、ボカロ文化が広がるほどに、ますます難しくなっていくように思えます。私は、初音ミクは一つの決まった形を持たず、無数の解釈の中でその都度新たな姿を与えられる存在であるため、特定することは不可能なのではないかと思っています。
プレイヤー、普遍的存在、他者、代弁者——。この記事で紹介した楽曲でのミクの姿は、ほんの一部に過ぎません。作品の数だけ、クリエイターの数だけ、そしてリスナーの数だけ異なる初音ミクが存在します。それは決して“初音ミクの本質はこれだ”と決め付けることができないことを意味します。しかし、それこそが初音ミクというキャラクターの面白さであり、多くの人に愛され、表現の媒体として機能し続けている理由なのではないでしょうか。
だからこそ、あなたが思う初音ミクは、きっとあなたにとっての、正しい初音ミクです。あるときは誰かが描いたミクがあなたの心を代弁し、またあるときは遠い他者の声として響く。そんな風に初音ミクという存在は、あなたの中のミクとして生き続けるのかもしれません。
私の考える初音ミク像も、また一つの解釈に過ぎません。だからこそ、この記事の最後に、この言葉を添えたいと思います。
“特定しないでね。”
歌を超えて声を超えて文化として響くボーカロイド/ボカロP ぱりぱりさらうどん/『FEAT CONTEST 2024』plug+賞 連載①

注目記事
-
#基礎から練習
やまもとひかる 爆誕!! スラップ・ベースっ子講座
-
#ゼロから学ぶ
きつねASMRと学ぶASMRの始め方
-
#上達のヒント
超学生のネット発アーティスト・サウンド解剖。
-
#ゼロから学ぶ
マンガで楽理を学ぶ!「音楽の公式」
-
#基礎から練習
ボカロPに学ぶ。ボカロ曲の作り方
-
#上達のヒント
宮川麿のDTMお悩み相談室
-
#ゼロから学ぶ
初心者の頼れる味方! はじめての楽器屋さん