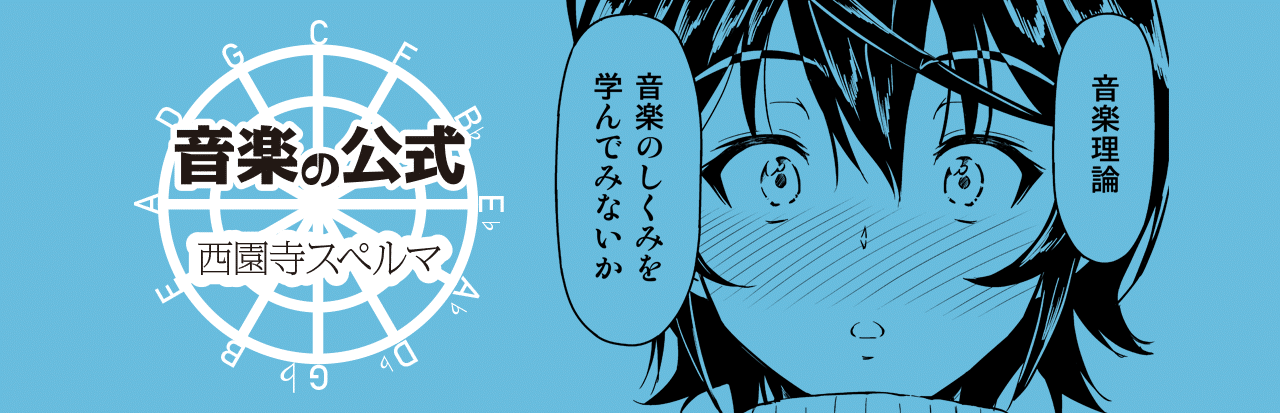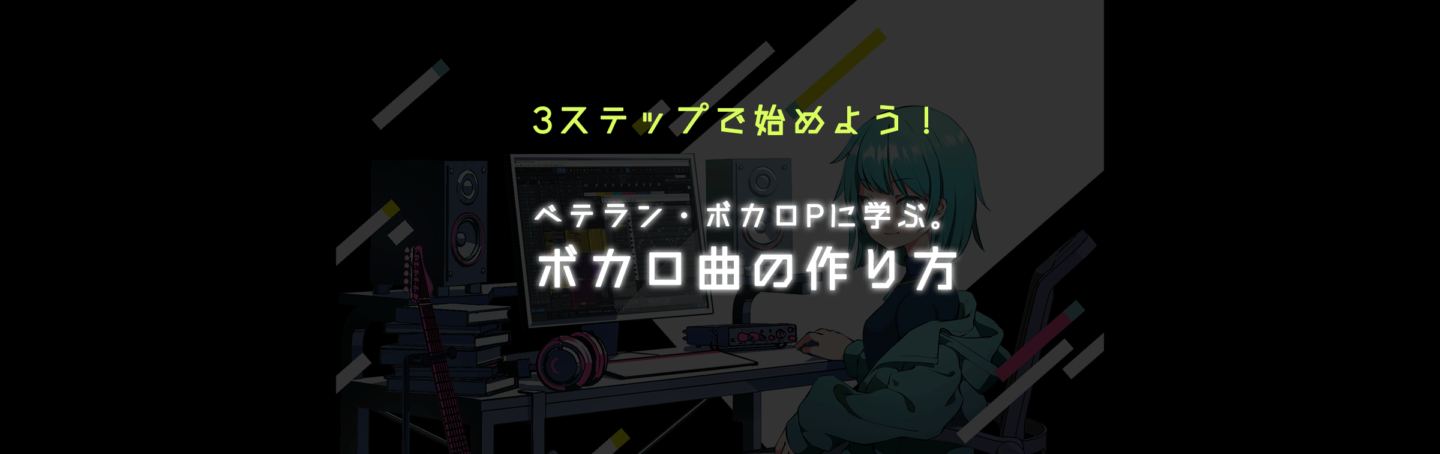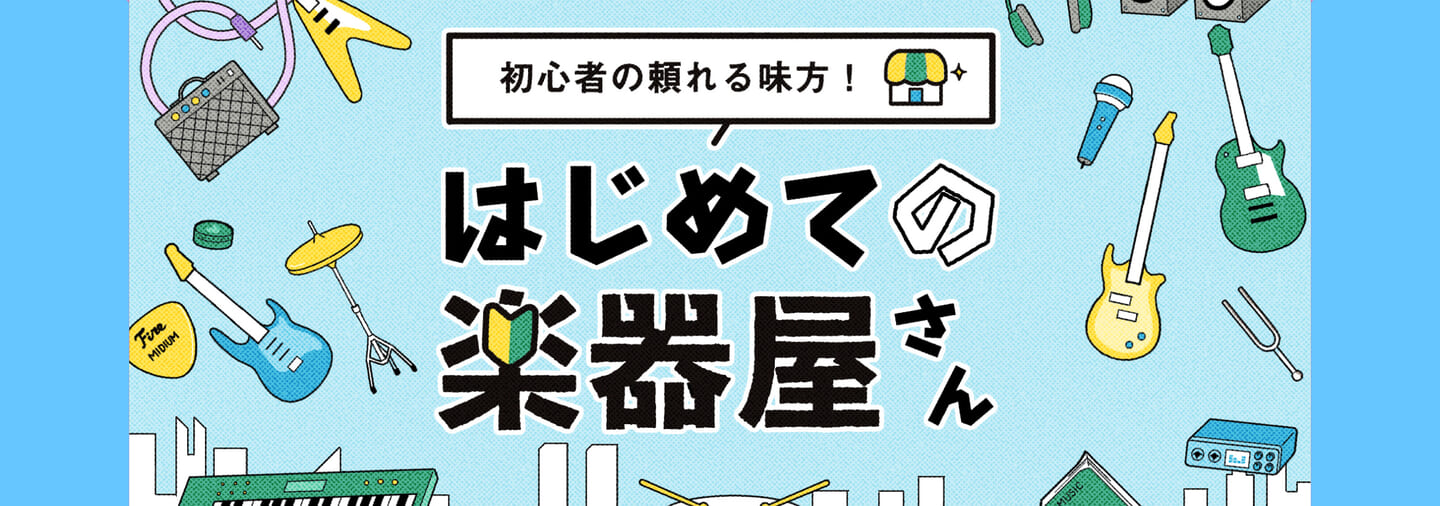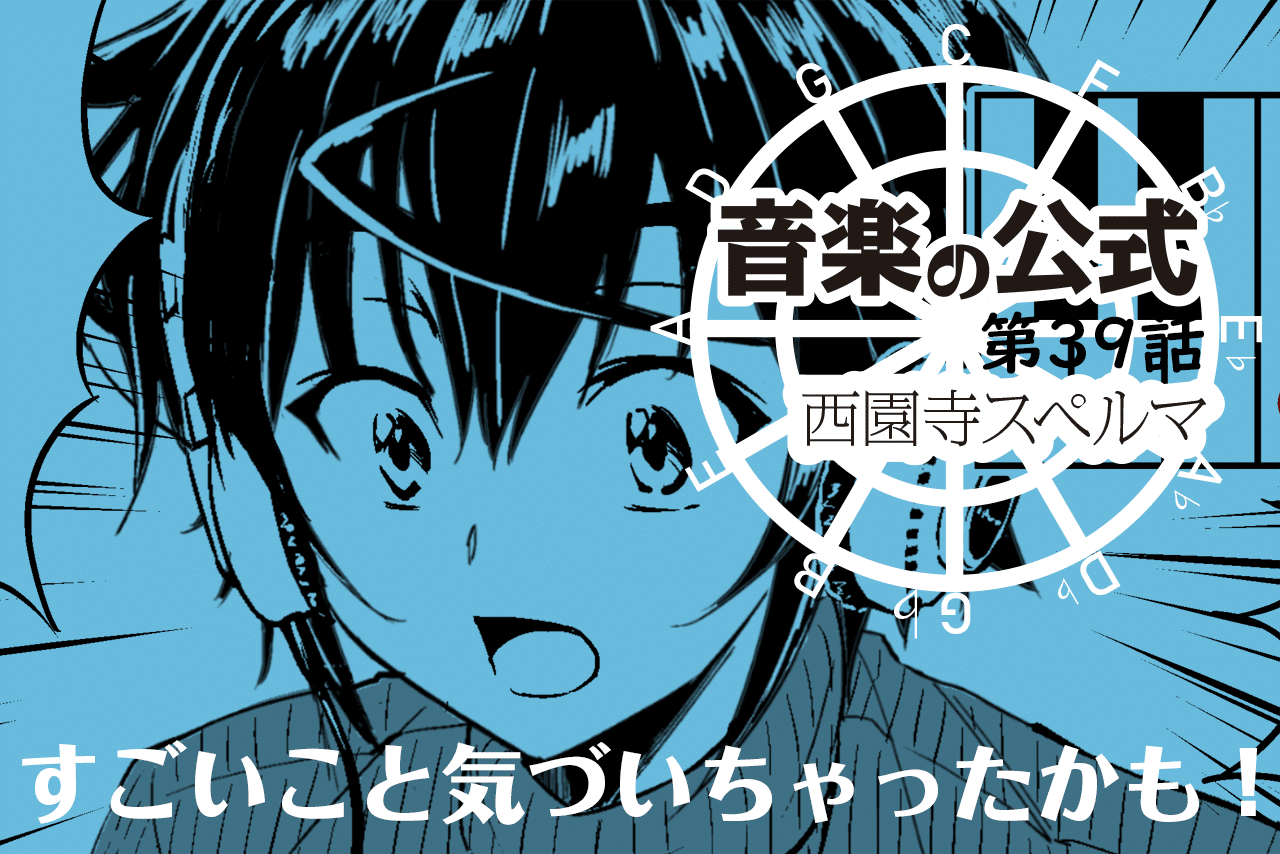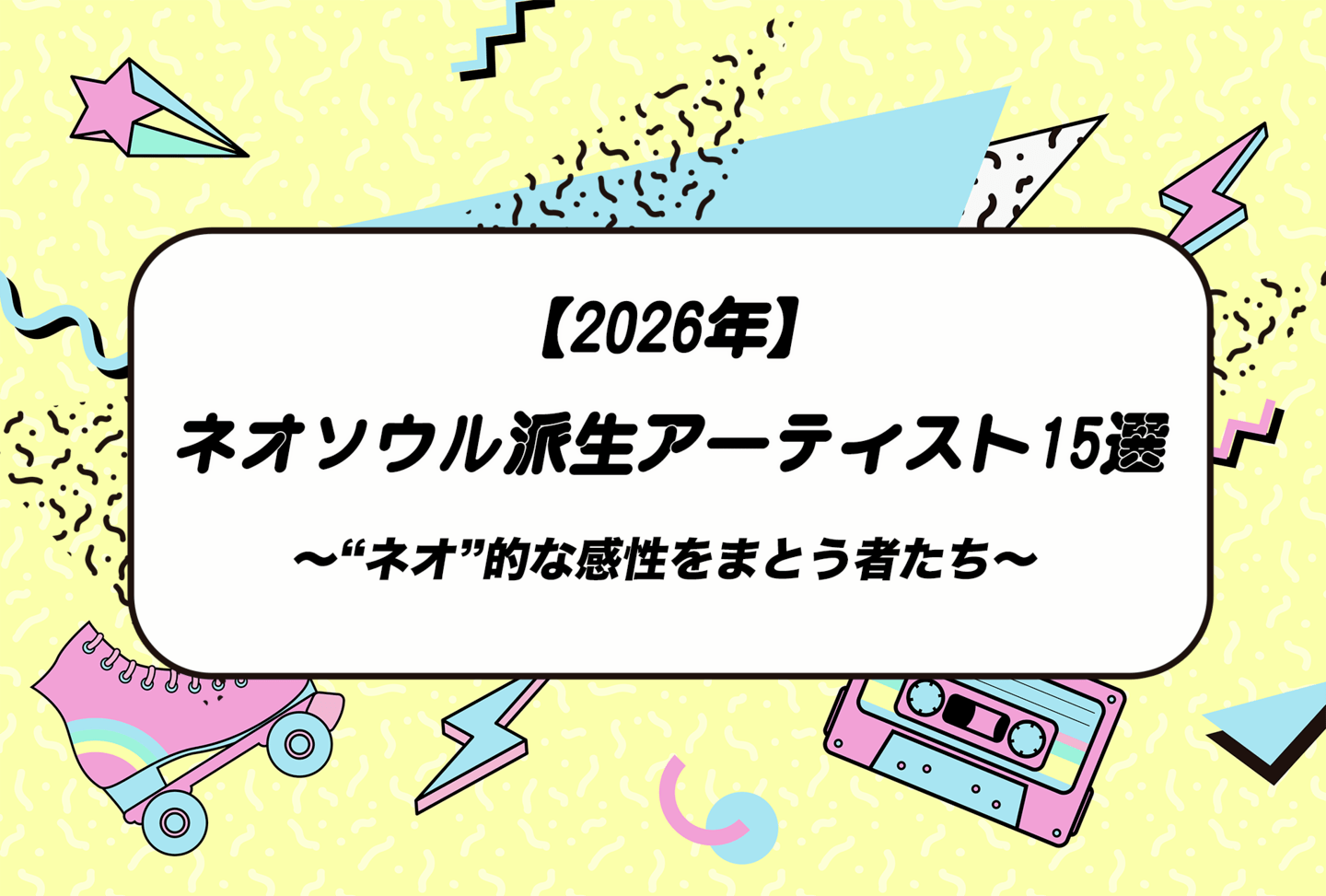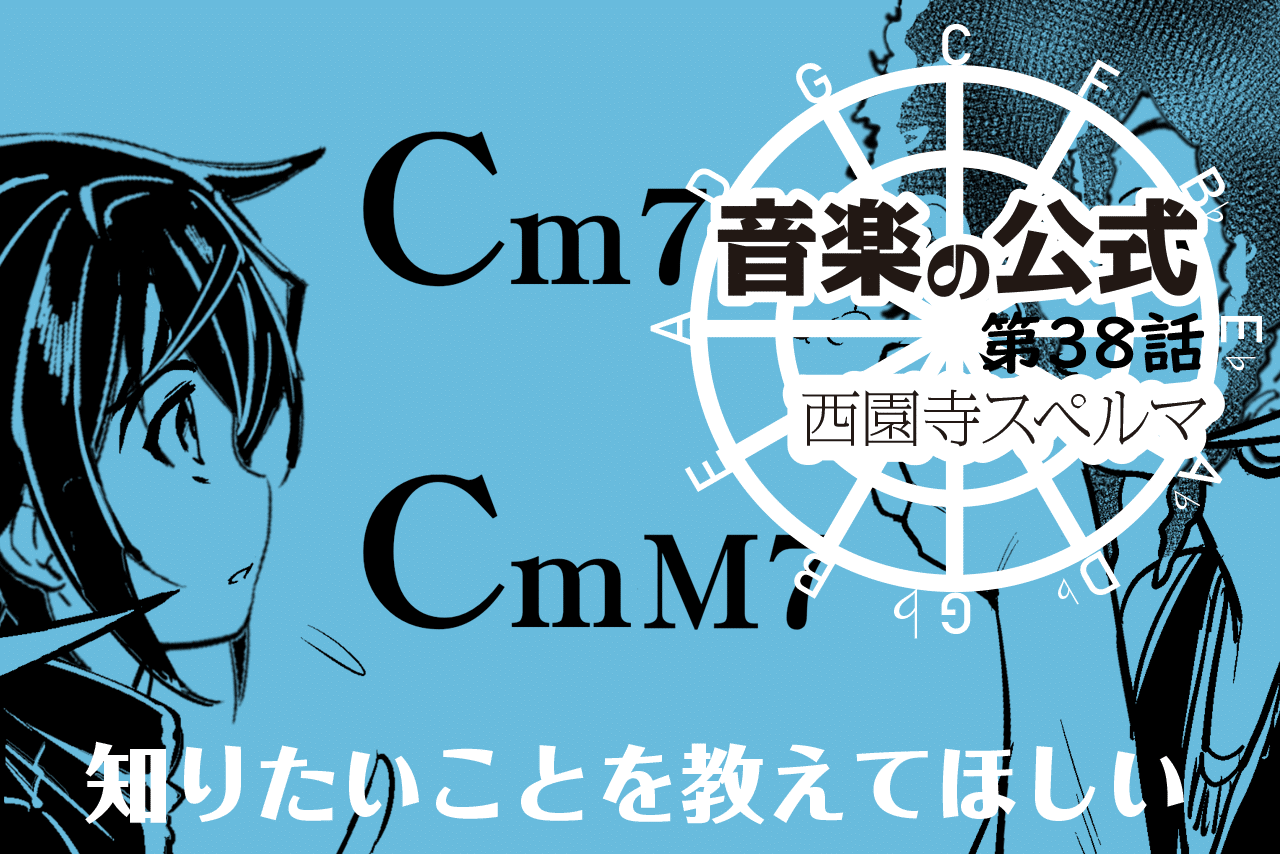文:ぱりぱりさらうどん
編集:濱田侑佳(plug+編集部)
画像:文章内にURLを記載
目次
はじめに

はじめまして。ボカロPのぱりぱりさらうどんと申します。
クリエイター・マッチング・サービスのFEATが主催した、歌モノ楽曲を対象としたコンテスト『FEAT CONTEST 2024』にて「plug+賞」をいただき、この文章を書くに至りました。ありがたい話です。
せっかくこのような機会をいただいたので、「plug+賞」の審査基準にもあった「合成音声が使用されていること」と「顕著な革新性」の関係について考えてみたいと思います。本稿は私が執筆する連載『ぱりぱりさらうどんと巡るボカロの世界』の第一弾目であり、全四回を予定しています。
ボーカロイドは“歌うもの”という印象が強いですが、実際に投稿されているさまざまな楽曲を聴いて、MVを観てみると、それ以外の使われ方も数多く存在していることが分かります。本稿では、ボーカロイドが担う役割が“歌うこと”に留まらない点に注目し、いくつかの楽曲を例に挙げながら、ボーカロイドを使って音楽を制作することがどれだけ幅広い可能性に満ちているかを考察していきたいと思います。
もちろん、ボーカロイドやボカロ曲の解釈は人それぞれです。私は、特定の考え方を押し付けるつもりはないので、一つの視点として“こんな捉え方もあるんだな”と思っていただければ幸いです。それでは、本題へと進みましょう。
アメリカ民謡研究会(Haniwa)「宗教に犯されているのではないか。 / 結月ゆかり」
結月ゆかりさん、あなたの感情は人間の模倣でしょうか。それとも?~ボーカロイド×ポエトリー・リーディングの可能性~
この楽曲では、ボーカロイドは歌唱するのではなく、私たちに詩を語りかけています。このように詩を朗読する手法は、ポエトリー・リーディングと呼ばれるものです。こうした表現は近年のボカロ・シーンでも多く見られるようになったため、取り上げてみます。
「宗教に犯されているのではないか。」の歌詞では、合成音声とは何かという問題に留まらず、音楽とは何かを問うているように思います。私はそれが合成音声の持つ無機質性とともに、ポエトリー・リーディングによって語られることで、あなたには感情があって、私には何もないということがより強く伝わってくるのだと考えています。
歌詞をよく読んでみますと“私”の言動は嫌というほど主観的です。五感に基づいた描写に、強い感情や確信が滲む表現。それはまるで、機械が人間の思考をわざとらしく真似たかのようです。0:40ではブレイクとともに<可哀相に。>という言葉が発音されており、この表現からはまるで結月ゆかりさんが“ほらほら、人間ってこう言われたら腹立つんでしょ?”と言わんばかりに、我々の怒りの感情を扱いこなしているような印象を受けます。その後結月ゆかりさんは、目を逸らしたくなる現実を描写するような言葉に対し、人間の複雑な心情を汲み取ることなく<それは命と同じなのに。>と、一蹴。
さて中国語の部屋という思考実験があります。簡単に説明しますね。
中国語を全く理解していない人が、小部屋の中で“AにはBを書く”と指示されたルール・ブックを使って、中国語の質問に対し適切な回答を作成し、部屋の外へ返します。外部の人には部屋の中の人が中国語を理解しているように思えますが、実際はそうではありません。これは哲学者ジョン・サールが、コンピュータが記号処理をして適切な回答を導き出しても、問題自体を理解していることにはならないことを示したものです。「宗教に犯されているのではないか。」のゆかりさんも、まさにこの部屋の中の人のように、思考のシステムだけで存在しながら、本当の意味では思考していないように思います。
人間は、自分の思考を完全に客観視することができません。なぜなら、客観視しようとするその行為自体も、思考によるものだからです。しかしボーカロイドはそもそも思考を持たないため、人間と思考とを切り離し、それを記号として表現することができます。だからこそ、ボーカロイドは客観視された思考の象徴として存在することができるのです。しかし、それは本当の意味での思考と呼べるのでしょうか?
誰かを救う宗教という言葉は、時に肯定的にも否定的にも受け取られます。信じるか、疑うか。どうやら私たちには感情が、知識が、概念があるみたいです。“それに従って判断を起こせ。”
松傘 & MSSサウンドシステム「エイリアン・エイリアン・エイリアン / 初音ミク」
え?怖。なんかやべえ猫が初音ミクを名乗っているんですけど……。~ボーカロイドだからこそ生み出せる唯一無二のフロウ~
このミクの歌は、歌声でしょうか。ラップでしょうか。この曲には寝言のような、呻き声のような独特なフロウがあり、歌っているというよりかは、ヒップ・ホップというカルチャーを駆使してこちらに何かを“訴えかけている”というような印象を受けます。ですがそれにしたって、内容も分からないし、不気味。表示される歌詞と実際にミクが歌う言葉は果たして一致しているのだろうか? 英語訛りの日本語ラップが醸し出す雰囲気は圧倒的に異質であり、未知との遭遇を感じさせます。
かわいらしく、人間に愛される存在の猫に擬態したソレは、同じく人間から電子の歌姫と愛されるミクを自称する。“私は猫だからミクだから無害ですよ”とこちらを油断させて捕食。絶叫。私はそんな印象を受けたのですが皆さんはどうでしょうか。
この曲において、擬態するエイリアンが発する言葉は、動物的な本能を感じさせる内容のものです。しかし、もしこの曲で表示されている歌詞が、エイリアンの発する言葉を理解できない我々による、空耳で予想されてしまったものだとしたら……。私たち人間は猫、ないしは動物から何かを訴えられ、その言葉を解釈しようとするときに“どうしたの?お腹すいたの?”、“眠たいの?” などと問い、動物的な本能という共通項を介して、一方的な解釈をします。人間は猫ではありません。人間はエイリアンではありません。しかし同じ生物です。果たして、擬態するエイリアンが発する言葉の真意とは?
松傘さんが提供するミクのフロウは、人間には真似できない唯一無二のものです。また松傘さんは初音ミクを、「ミックホップのはらわた」や「初音MICの感染」などのほかの楽曲でも、理解できない異端な存在として描きます。私は「エイリアン・エイリアン・エイリアン / 初音ミク」にも、独特のグロテスクな世界観を感じます。再生する度にあなたの耳から脳髄(編中:のうずい)へと侵入し、やがて身体をも蝕む(編中:むしばむ)。それは、狂気と快楽が入り混じるドープなソング。
r-906「the Hole / 足立レイ」
足立レイは投げかける。 “声とは何か”を投げかける。~電子音と歌声の境界線はどこにある?~
「the Hole」は楽曲に合成音声ソフトの足立レイを使用していますが、よくある歌モノのように、リード・ボーカルとして採用しているわけではありません。r-906さんが生み出すドラムンベースの世界を構築する素材として、シンセサイザーやリズム隊といった楽器の役割を果たしています。
そしてこの曲での足立レイの歌声は楽曲の構成要素として機能しつつも、r-906さんが組み立てるほかの楽器の音と違和感なく溶け合っており、ドラムンベースとの相性が抜群です。このことは“ボカロは合成音声ソフトという一種の機械であるから、メイン・ボーカルというより、オケを構成する楽器として扱うこととの相性が良いのだなあ。”と、そう簡単に片付けられる話ではありません。
知っている方も多いと思いますが、この楽曲で使用されている足立レイには、中の人=声の提供者が存在しません。通常の合成音声ソフトは人間の声を元にして作られています。しかし足立レイの声はピー音(Sin波)の組み合わせによって作られているので、完全に人工的な音声合成ソフトになっているのです。この辺りの詳細は、開発者であるみさいるさんの動画をぜひチェックしてみてください。すごいので……!
結論から言うと「the Hole」では、ピー音の組み合わせによって作られた人工的な声を、再びシンセサイザーのように使用するという、転倒した現象が起こっています。元々機械音として生まれたものが、声として機能し、そして再び楽器へと戻る。発生と利用の逆転現象。しかしながら確実に合成音声として存在している……。声と電子音の境界が曖昧になり、そもそも‘声とは一体何なのか“という概念そのものが揺さ振られます。
読谷あかね「逃ゲガチ / 重音テトSV」
文化によって歌われるボーカロイド~沈黙が語るボーカロイドの可能性~/読谷あかね「逃ゲガチ / 重音テトSV」
この曲は、インストゥルメンタル(以下、インスト)です。「逃ゲガチ」を歌うのは重音テト……のはずでした。しかしMVにテトの姿はなく、曲中でテトの歌声が流れることもありません。しかしサムネイルやタイトル、クレジットなどには重音テトの姿、文字が記されており、そこから私たちは居ないはずの重音テトの存在を認識します。そして、流れ続けるインストと、<タスクが大爆発>、<降り積もったプレッシャー>などといった歌詞を見て、“ああ、テトは歌うことが嫌になって逃げ出したんだな”と気付くのです。
通常、私たちは歌声を聴くと、それを発している“誰か”の存在を自然と意識してしまいます。それが人間の声ならもちろんのこと、たとえボーカロイドなどであっても、そこに何らかの主体を感じ取るのです。しかし「逃ゲガチ」にはボカロによる歌唱がない。声を失い、姿を消したテトは、本来ならばただの無となるはずです。
ですが私は、実際にはその逆の現象が起こっていると考えます。この曲のMVでは、ボーカルが抜け落ちているにも関わらず、音楽は止まらない。<どうせ僕がいなくたって 世界は回る>という歌詞の通り、インストが進行し、歌詞は画面に映し出され続けます。このようなテトの不在は楽曲全体を通じて私たちに強く刻み込まれており、逆にその存在を強く突き付けているように思います。
この曲の作者である読谷あかねさんは、2025年1月21日(火)に放送されたニコニコ動画の番組『はろー!にゅ~みゅーじっく!vol.24』内で、重音テトが元々エイプリル・フールのジョークとしてネット掲示板で制作され、等身大のキャラクター設定であることに対し、“インターネットの端っこにいる人たちの味方になってくれる存在”と語りました。そして、“嘘がテーマのキャラクターだからこそ、実験的な作風にも寛容であり、可能性が大きい”とも話しています。その言葉の通り、この曲のテトはまさしく実験的です。
皆さんは歌を放棄して姿を消すテトの行動を、どのように思いましたか? 私は“テトならやりかねない”と思いました。きっと同じように考える人はたくさん居るのではないでしょうか。重音テトは歌声合成ソフトとしても、ボカロ・キャラクターとしても、今日のボカロ・シーンで流行している。この楽曲の歌詞からは、その流行に疲れ果てたテトの姿が浮かび上がってくるように思います。また読谷さんが指摘しているように、重音テトが掲示板発のキャラクターであり、“嘘”がテーマにある存在であることから、「逃ゲガチ / 重音テトSV」という楽曲の構造そのものが“嘘”だと言われても納得できてしまう……。私は、こういった昨今重音テトのムーブメントや、キャラクターとしての特異性が反映されることで、“テトなら歌を放棄して逃げかねない”という感覚がリスナーの間で共有されているのではないかと考えました。
重音テトとは単なる歌声合成ソフトではなく、コミュニティの中で独自の人格を持つ存在としてユーザーに認識されていると思っています。だからこそ、テトが逃げたと言われても、私たちは受け入れる。私はこれを、使用されたボーカロイドのキャラクター性がその作品に深みを出すという、ボーカロイド文化の持つ現象の一つだと考えます。そして「逃ゲガチ」は、その傾向が特に強い作品であるとも思いました。
歌うべきボーカロイドが歌わなかったとき、その空白を埋めるのは誰なのか……。私は、“ボーカロイドという文化によって歌われている”と考えます。重音テトが歌わなかったとしても、楽曲は公開され、リスナーの間で語られ、考察される。そして、重音テトが歌わなかったことすらも、文化の中で意味を持つようになる。重音テト、ひいてはボーカロイドという存在が、オリジナルとしてではなくボーカロイド・カルチャーの創造物として機能し、文化の中で生き続けるのです。
色々と語りましたが、私はこの曲を、ボーカロイドという存在そのものを問い直す作品だと思っています。ボーカロイドは基本的に“歌うもの”ですが、「逃ゲガチ」においては、その前提が覆されている。ボーカロイドとは何なのか? ただの歌う道具なのか? この曲は、その問いを私たちに投げかけてくる。文化の中で今もなお響き続ける声を背に、重音テトは確かに‘逃ゲガチ“した。
最後に
ボーカロイドとは何か?
今回は、ボーカロイドを歌うものとして扱うのではなく、音楽表現に用いている楽曲という視点から4曲を選び、考察しました。もちろん、これは私個人の解釈に過ぎず、ボーカロイドに対する感じ方や考え方は人それぞれ違うはずです。きっと、これを読んでいる皆さんにも、自分だけのボカロ像があるのではないでしょうか。ボーカロイドの魅力は、その多様性にあります。だからこそ、ぜひあなた自身の視点でも考えてみてほしいと思います。
次回も、具体的な楽曲を挙げながら、ボーカロイドが持つ表現の可能性について、引き続き考えていきます。ボカロという存在が、これからもあなたの生活に寄り添い、彩りを与えてくれることを願っています。
注目記事
-
#基礎から練習
やまもとひかる 爆誕!! スラップ・ベースっ子講座
-
#ゼロから学ぶ
きつねASMRと学ぶASMRの始め方
-
#上達のヒント
超学生のネット発アーティスト・サウンド解剖。
-
#ゼロから学ぶ
マンガで楽理を学ぶ!「音楽の公式」
-
#基礎から練習
ボカロPに学ぶ。ボカロ曲の作り方
-
#上達のヒント
宮川麿のDTMお悩み相談室
-
#ゼロから学ぶ
初心者の頼れる味方! はじめての楽器屋さん